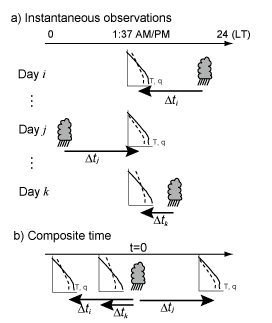 熱帯の対流雲は、水蒸気収束や地表面からの熱フラックスなど大気を不安定化させる大規模強制力に抗い、
大気状態を安定化させようとする「調停役」の役割を果たすと考えられることがあります。
そのような対流による中立化効果は、
(Aarakawa and Schubert, 1974を初めとする)研究者の一派により準平衡仮説として定式化され、
多くの積雲パラメタリゼーション手法に広く取り入れられてきました。
一方最近の研究で、当初提案された形の準平衡仮説に対し変更を迫る観測的事実が指摘されています。
熱帯の対流雲は、水蒸気収束や地表面からの熱フラックスなど大気を不安定化させる大規模強制力に抗い、
大気状態を安定化させようとする「調停役」の役割を果たすと考えられることがあります。
そのような対流による中立化効果は、
(Aarakawa and Schubert, 1974を初めとする)研究者の一派により準平衡仮説として定式化され、
多くの積雲パラメタリゼーション手法に広く取り入れられてきました。
一方最近の研究で、当初提案された形の準平衡仮説に対し変更を迫る観測的事実が指摘されています。
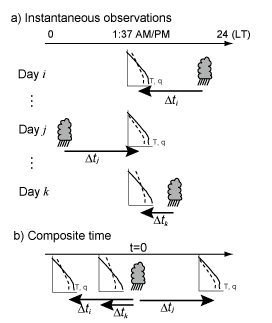 熱帯の対流雲は、水蒸気収束や地表面からの熱フラックスなど大気を不安定化させる大規模強制力に抗い、
大気状態を安定化させようとする「調停役」の役割を果たすと考えられることがあります。
そのような対流による中立化効果は、
(Aarakawa and Schubert, 1974を初めとする)研究者の一派により準平衡仮説として定式化され、
多くの積雲パラメタリゼーション手法に広く取り入れられてきました。
一方最近の研究で、当初提案された形の準平衡仮説に対し変更を迫る観測的事実が指摘されています。
熱帯の対流雲は、水蒸気収束や地表面からの熱フラックスなど大気を不安定化させる大規模強制力に抗い、
大気状態を安定化させようとする「調停役」の役割を果たすと考えられることがあります。
そのような対流による中立化効果は、
(Aarakawa and Schubert, 1974を初めとする)研究者の一派により準平衡仮説として定式化され、
多くの積雲パラメタリゼーション手法に広く取り入れられてきました。
一方最近の研究で、当初提案された形の準平衡仮説に対し変更を迫る観測的事実が指摘されています。
準平衡仮説を観測と比較し検証するため、湿潤対流の前後で見られる熱帯および亜熱帯大気の熱力学的進化を 衛星データ解析を通じて探る研究を行いました。 熱帯降雨観測衛星(TRMM)およびAqua衛星の上空通過地方時差が日々刻々と変化することに着目し、 この観測時差で定義される時間軸上に衛星データを投影し、 数時間から数日スケールのコンポジット時系列を作成する手法を考案しました(右図)。
深い対流雲と雄大積雲(対流圏中層に雲頂を持つ積雲)のそれぞれについて、
対流に対する大気強制力と大気応答を調べました。
熱帯中心部では、
深い対流が大気境界層の水蒸気を自由対流圏に逃がす迅速な換気効果を促すことを見出しましたが、
それに先立ち大気境界層の水蒸気はじわじわと増加を続けており、
平衡状態への調整機構が間断なく機能しているとまでは言えませんでした。
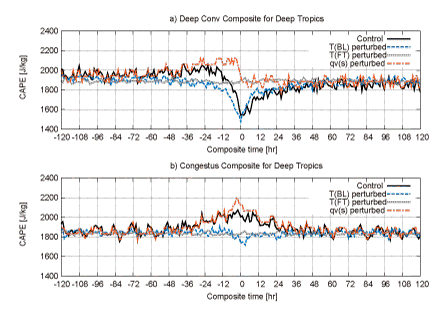 対流有効位置エネルギー(CAPE)の時間進化(左図の黒い曲線)は、
大気境界層の水蒸気の寄与(赤い曲線)だけでなく、
同時に進行する境界層の冷却効果(青い曲線)によっても多大な影響を受けています。
CAPEは対流に先立つ12時間で急速な下降を見せたのち、冷却偏差が回復する1ないし2日間のあいだに
回復することがわかります(左図a)。
一方、湿潤対流が雄大積雲だけでもたらされ周囲に深い対流を伴わないときは
CAPEのふるまいは大きく異なり、CAPEは雄大積雲が発達するまで1-2日をかけてわずかに増加し
その後やはりゆっくりと最初の状態まで減少します(左図b)。
つまり、対流雲が対流圏全層を貫くほど深く発達しないときには、
熱帯の中心部であっても対流調節は有効には機能しないことがわかります。
対流有効位置エネルギー(CAPE)の時間進化(左図の黒い曲線)は、
大気境界層の水蒸気の寄与(赤い曲線)だけでなく、
同時に進行する境界層の冷却効果(青い曲線)によっても多大な影響を受けています。
CAPEは対流に先立つ12時間で急速な下降を見せたのち、冷却偏差が回復する1ないし2日間のあいだに
回復することがわかります(左図a)。
一方、湿潤対流が雄大積雲だけでもたらされ周囲に深い対流を伴わないときは
CAPEのふるまいは大きく異なり、CAPEは雄大積雲が発達するまで1-2日をかけてわずかに増加し
その後やはりゆっくりと最初の状態まで減少します(左図b)。
つまり、対流雲が対流圏全層を貫くほど深く発達しないときには、
熱帯の中心部であっても対流調節は有効には機能しないことがわかります。
上で述べたコンポジット手法を改良の上さらに活用すると、
熱帯大気の水蒸気収支・熱収支解析に応用できることを次に紹介します。
ここで用いる衛星センサは、レーダ(TRMM PRおよびCloudSatレーダ)や
赤外・マイクロ波サウンダ・ユニット(Aqua衛星搭載AIRS/AMSU)から
マイクロ波放射計(Aqua衛星搭載AMSR−E)やマイクロ波散乱計(QuikSCAT衛星搭載SeaWinds)に及びます。
気温や水蒸気、積雲雲量、海上風といった大気パラメータの衛星観測値を、
前項で概説した方法と同様にTRMMが検出した対流との時間差に対してコンポジット解析を行い、
統計的に連続な時系列を得ます。
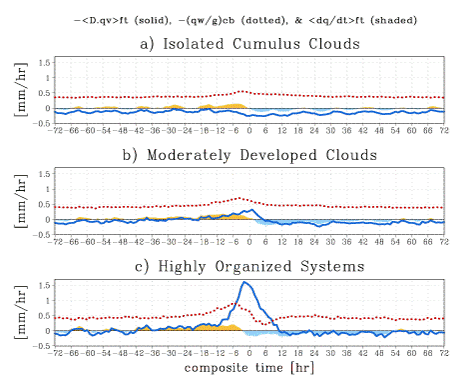 AIRSが観測した気温・湿度鉛直分布(雲の影響を除去した推定値)は、
半解析的に導出した雲内気温や湿度と組み合わせて、
大規模場全体の平均値を代表する均気温・湿度場を求めます。
そしてこれらの推定値を水蒸気収支・熱収支方程式に代入し、
雲底の上下2つの大気層それぞれにわたって鉛直積分を行います。
すると、従来は衛星観測値のみから導出することの難しかった、
自由対流圏内での水蒸気・乾燥静的エネルギー(エントロピーの近似値)の水平収束および
雲底における鉛直フラックスを求めることが可能となります。
AIRSが観測した気温・湿度鉛直分布(雲の影響を除去した推定値)は、
半解析的に導出した雲内気温や湿度と組み合わせて、
大規模場全体の平均値を代表する均気温・湿度場を求めます。
そしてこれらの推定値を水蒸気収支・熱収支方程式に代入し、
雲底の上下2つの大気層それぞれにわたって鉛直積分を行います。
すると、従来は衛星観測値のみから導出することの難しかった、
自由対流圏内での水蒸気・乾燥静的エネルギー(エントロピーの近似値)の水平収束および
雲底における鉛直フラックスを求めることが可能となります。
解析の結果、主に以下のことが明らかになりました。 1)孤立した積雲(右上図)に先立つ自由対流圏水蒸気の主要な供給源は、 雲底における鉛直水蒸気輸送(右図の点線)であるが、 一方高度に組織化した降水システムが発達する際(右下図)は、 水蒸気の水平収束が圧倒的となる。 2)自由対流圏の非断熱加熱は、予想されることだがほぼ瞬時にほとんど解消する。 3)雲対流に伴う渦輸送による自由対流圏の湿潤化効果は、 背景場においては雲底における全水蒸気フラックスの半分程度を占めているが、 高度に組織化した降水システムの発達下では、 大規模平均上昇流がもっぱら雲底フラックスの時間変動の要因を担う。 なお、自由対流圏の水蒸気が雄大積雲量と密接な相関があることが知られているが、 この相関は積雲による渦効果よりむしろ大規模力場よる水蒸気鉛直輸送の効果が効いているようである。
この話題に関連する文献
| ホーム | 新着情報 | 研究紹介 | 研究業績 | メンバー | 講義 | HyARC | English | |||||||